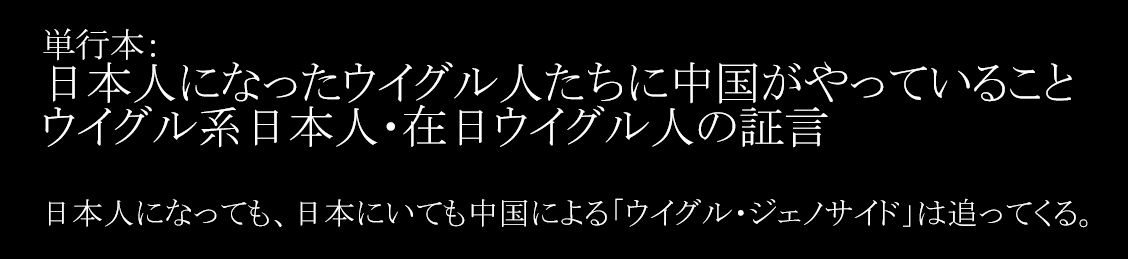現代ビジネス 2021/8/20
あるカザフ人女性の証言
長いあいだ書こうと思って、どうしても書けなかった。草思社から出ている『重要証人: ウイグルの強制収容所を逃れて』という本についてだ。
なぜ、書けなかったかというと、ちゃんと読めなかったからで、正直にいうと、今でも完璧には読んでいない。あまりにも残酷そうなところに差し掛かると、自己防衛本能が働き、「ここは読むな」と警告を発する。それだけで、私は怖くて震えそうになる。何度かトライしたが、警告はいつも同じところで来た。
同書は、サイラグル・サウトバイというカザフ人女性の話を、ドイツ人ジャーナリストのアレクサンドラ・カヴェーリウス氏がまとめたものだ。1976年、サウトバイ氏は東トルキスタン(新疆ウイグル自治区)で生まれた。ここには、カザフ、ウイグルなど多くの民族がいる。彼らはイスラム教徒だ。
サウトバイ氏はいわゆるエリートで、イリ自治区の大学を主席で卒業し、97年からは医師として働いた。イリの人口構成は90%がカザフ人だが、すでに中国の侵略は進んでおり、医師の80%は中国人。大学では研究や解剖用に、出所不明の健康な臓器がふんだんに提供されていたという。
その後、彼女は母親の看病のため医師をやめ、地元に帰って教員の研修を受けた。公職に就くには入党が必要となり、2001年、共産党員となった。2004年、やはり教員であったカザフ人の男性と結婚し、2005年に娘が生まれた頃は、彼女はまだ将来に対する希望を全て失っていたわけではなかった。
2006年、学校で使用する言葉が、カザフ人にとっては外国語である中国語となった。教師の8割が中国人となり、カザフ人は職を失った。紆余曲折は省略するが、2009年には長男も生まれた。そしてその頃、党では自己批判制度が導入され、職場で全員が、自分の過ちを中国語で記すことが義務となった。
2009年、ウイグル人少女のレイプをきっかけに、ウルムチで大規模なデモが起きたが、中国人兵士がウイグル人の服を着て中国人を攻撃し、その報復と称してウイグル人とカザフ人が大量に虐殺されたという。
2014年には強制収容所の建設も始まった。しかし、その頃にはすでに、習近平国家主席のポスターがあらゆるところに飾られ、カザフ人やウイグル人は生活の糧を失い、ウイグル自治区(東トルキスタン)全域が次第に刑務所のようになっていった。
そのうち公務員のパスポートが取り上げられ、外国には出られなくなった。サウトバイ氏の夫は退職していたため、パスポートがあった。そこで彼らは大きな決断をする。夫と子供達だけでも、まずここを脱出するべきだと。
ここを出て世界に知らせるために
2016年、3人が旅行を装ってカザフスタンに旅立つのを、サウトバイ氏は「必ず後から行くから」と誓いながら見送った。その後まもなく、チベットで文化を破壊し、人々を虐殺した人物が、東トルキスタンの新しい党書記に任命された。
中国政府による統制は進んだ。顔写真、網膜、声紋による絶対に誤魔化せないIDカードが作られ、健康診断が行われた。外国との交信が断たれ、サウトバイ氏は通信アプリで夫や子供と話すこともできなくなった。あらゆるところに監視カメラと警備員が配置され、突然、消える人が増えた。
そして、2017年、ついにサウトバイ氏も連行され、家族がカザフスタンにいることを責められた。その後も、頭に布が被せられた連行と釈放が何度か繰り返された。
その年の11月、サウトバイ氏が目隠しのまま連行されたのは、いつものように警察ではなく、収容所だった。しかも、ここで教師として働くために。
収容所に関する話は、ご自分で読まれたい。全てを読みきれていない私だが、人間がここまで残酷になれるのかと、信じられない思いに襲われた。古代でも中世でもなく、今、起こっている話だということを考えてほしい。
サウトバイ氏は収容所で、「契約は極秘、収容者に話しかけることも、感情を表すことも、許可なく質問に答えることも禁止」という誓約書を書かされ、24時間ライトのついた監視カメラ付きの部屋をあてがわれた。何か一つ間違えば死刑だ。
一方、収容者は16㎡ほどの部屋に20人ほどが詰め込まれ、いつも手錠と足枷をはめられている。トイレはなく、部屋にバケツが1個置いてあるだけ。この収容所には、2500人ほどが収容されていたという。収容者は、ウイグル全体ですでに100万人に上ると言われている。
彼女を何より苛んだのは、少女が集団で公開レイプされようが、収容者が拷問されようが、助けることはもちろん、感情を示すことさえ許されないことだったという。ちょっとでも同情や動揺の表情がカメラに捉えられたら、同じ運命になるだけだ。
一度、「助けて!」と縋られた老女に手を添えたら、中世のような拷問道具の並ぶ部屋に連れて行かれて、電気椅子にかけられた。抵抗など誰の助けにもならないことはすぐに理解できた。
この時、サウトバイ氏は生き延びようと決心した。子供達に会うことだけを考えた。そして、ここを出て世界に知らせるために、全てを記憶しておこうと心に誓った。
夫と子供が待つカザフスタンへ
どんな残酷なシーンにも動じない彼女の態度が監督者たちに認められたのか、収容所に来てから5ヵ月目の2018年3月の夜中、彼女は自宅に戻された。翌日から復職したが、数日後に解任され、次の指示を待てと命じられた。
しかし、彼女は逃亡を決意する。夫と子供が待つカザフスタンへ。たとえ失敗して殺されても、このまま死ぬよりはましだった。同書ではここから、パスポートのない彼女が国境を越える様子が描写される。やはり、読みながら胸騒ぎで苦しくなる箇所の一つである。彼女はすでに心身ともに、ボロボロになっていた。
あたかも奇跡のようにカザフスタンへの電撃入国を果たした彼女は、家族と再会する。ただ、カザフスタンには既に中国の権力が伸びており、一家に平和な生活が訪れることはなかった。まもなくサウトバイ氏は拘束され、中国に送還される危険が迫った。
ところがその頃、カザフスタンで思いがけず大きな運動が巻き起こる。彼女の夫と義兄が、カザフの有名な人権活動家とともに、この件をビデオメッセージで発信した。すると、それがきっかけでカザフ人の怒りが燃え上がり、その輪が国中に広がっていった。カザフスタンには、中国の収容所に消えた家族や親戚を持つ人が大勢いたのである。
2018年7月、サウトバイ氏の裁判が始まった。罪状は「違法入国」。4度の公判は、その度に傍聴人が増え続け、国連、アムネスティや、欧米のメディアまでが注目するようになった。
この時、裁判所に面会に来た9歳の息子を、10cmほどのガラスの隙間から、食い付かんばかりに眺めているサウトバイ氏の写真がある。そのインパクトがもの凄くて、見ただけで涙が出そうになる。これほど母の愛情を表した写真を私は過去に見たことがあっただろうかと思った。草思社はこの写真を同書の裏表紙に使った。
判決は「6ヵ月の自宅監禁」となり、支援者とともに喜んだのも束の間、判決が下されたその日のうちに、ウイグル自治区にいる母親、翌日には妹が逮捕されたというニュースが入り、彼女は打ちのめされた。その後も、カザフスタンの秘密警察に脅される生活が続き、さらに滞在ビザも小刻みにしか延長されず、結局、追い詰められた一家はスウェーデンへの亡命を決意する。
現在、一家はスウェーデンにいるが、心の平安は訪れず、特に彼女の健康状態が芳しくないと聞く。拷問室から聞こえてくる声や、レイプの場に引き摺り出されていく少女たちの絶望的な眼差しが、今なお彼女の精神を蝕んでいる。母や妹との連絡もいまだに取れない。
たとえ何もできなくても
一方、ウイグルの人権弾圧は、最近、国際社会の注目を集めるようになり、あちこちで不満が高まっている。
英下院、カナダ下院、オランダ議会、リトアニア議会など、また大臣レベルでは米国務長官ブリンケン氏が、ウイグル自治区で起こっていることをジェノサイドと認定した。ニュージーランド議会、イタリア議会は、非難決議を採択している。米国やEUでは、中国に対する制裁も進んでいる。
日本では、今年の4月、日本文化チャンネル桜、アジア自由民主連帯協議会、ネット番組「ウイグルの声」、南モンゴルクリルタイ(世界南モンゴル会議)の各代表が連名で、国会議員の全員に公開質問状を送付した。内容は下記である。
【質問】貴方は中国政府がジェノサイドを行っていると認めますか。
一、ジェノサイドと認める。
二、ジェノサイドとは認めない。
三、多数の人権侵害や弾圧はあるが、ジェノサイドとは言えない。
四、わからない。
五、答えることを拒否する。
六、その他(その理由や説明をお書きください)
その結果、709名のうち、回答があったのが157名。そのうち、ジェノサイドと認めると答えた人が81名。認めないが1名、わからないが8名など。そして、552名は、この質問状を無視した(各議員の見解など詳細は、http://www.ch-sakura.jp/1633.htmlで見ることができる)。もちろん、今期の国会では「ジェノサイド決議」は提起されていない。
ただ、実は国会閉会の前日、下村政調会長や、高市総務大臣など数人が、「対中非難決議文」の国会提出を求め、二階幹事長が承認のサインをするところまで漕ぎ着けていたという。ところが、すんでのところでそれを止めた議員がいて、その理由が「あんまりこういうの(ウイグル問題)興味がないんだよな」だったとか。
ウイグルの人権弾圧には確たる証拠がないと主張している学者もいるので、それならまだわかるが、「興味がない」は、反対の理由としては最低ではないか。そんな政治家は、いったい何に興味があるのだろう。
『重要証人: ウイグルの強制収容所を逃れて』の編集者は、精神的な負担が大きくて体調を崩したという。それでも、これは伝えなければならないと思って、この本を世に出した。ジャーナリズムの王道だが、それに比べて、発信力に恵まれた大手紙やテレビ局の何と逃げ腰であること!
私たちは、たとえ何もできなくても、せめて知らなければならないことはあると、反省を込めつつ、いつも思う。何も知ろうとしなかったから、拉致の被害者を取り戻そうと考えることもなかった。チベットで起こっていたことも、南モンゴルで起こっていたことも、知ろうと思えば知ることはできたはずだが、もう手遅れだ。
だからこそ今、何もできない私だが、同書だけは紹介したいと思った。遅すぎることは承知だが、まだ完全に手遅れではないことを祈りつつ……。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/86443?imp=0