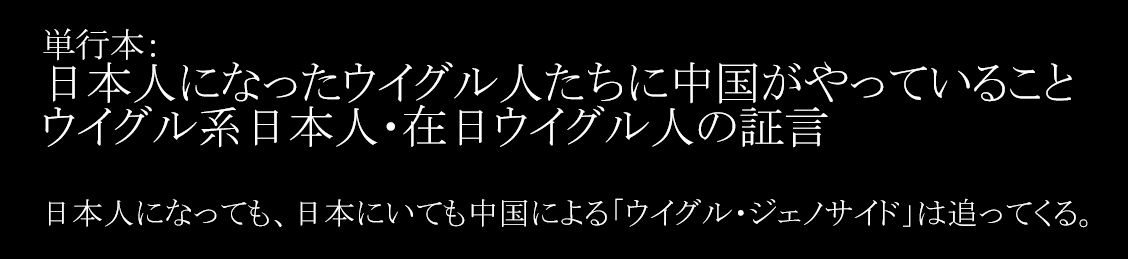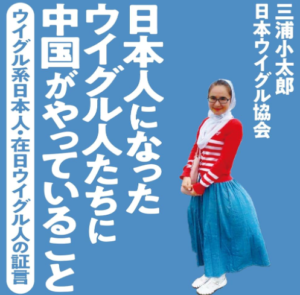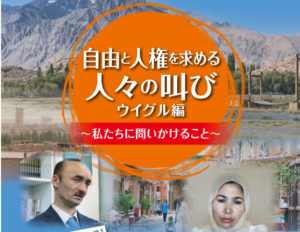2010年8月7日(土)被曝65周年にウイグルの核被曝を考える
- 2010/7/29
- お知らせ
2010年8月7日(土)被曝65周年にウイグルの核被曝を考える
2010年8月の広島での活動は無事に終了いたしました。
ご支援ご協力ありがとうございました。
※広島での活動の報告は、報告レポートのページをご覧ください。
2010年8月7日(土)被曝65周年にウイグルの核被曝を考える ~活動報告
2010年8月7日(土)被曝65周年にウイグルの核被曝を考える
【日時】2010年8月7日 午後16:30開場 16:45開始
【会場】広島県広島市中区袋町6番36号 広島市まちづくり市民交流プラザ 北棟5F 研修C
広島、長崎の被爆から今年は65周年になります。65周年にあたり日本ではあまり知られていないウイグル地域の核被曝について考えて行きたいと思います。
日本は最初の被曝国です、しかし唯一の被曝国ではありません、また最大の被曝国でもありません。中国では、新疆ウイグル自治区(東トルキスタン)の楼蘭付近で核実験を行い、周辺住民への甚大な健康被害と環境汚染とがもたらされています。
中国は1964 年から1996 年まで東トルキスタンのロプノールの核実験場において、46回、総爆発出力22メガトン(広島原 爆の約1370 発分)の核爆発実験を行いました。中国は核実験の被害状況を公表せず、現地調査も許可しないため、被害状況は長い間不明でした。
1992年にウイグル人、アザト・アキムベクが世界被曝者大会で被曝の状況を訴え、1998年にイギリスのチャンネル4が「Death on the Silk road」というドキュメンタリーでウイグルの被曝の状態について放送を行ないました。2008 年には札幌医科大学の高田教授がカザフスタンのデータを分析した結果、死傷者が100万人以上であると推論しました。
中国共産党の極秘資料によると75万人の死者が出たとも言われます。核実験の中でも「地表核爆発」は、砂礫などの地表物質と混合した核分裂生成核種が大量の砂塵となって、周辺および風下へ降下するため、空中核爆発と比べて核災害の範囲が大きくなります。このような危険な実験を、中国政府はウイグル人居住区で行いました。本集会では中国の核実験の一端を調査したドキュメンタリー「Death on the Silk road」を上映します。
またこの集会では昨年のウルムチ事件が「ウイグル暴動」として大きく報道されましたが現状はどうなのかについて少し話します。
被曝65周年にウイグルの核被曝を考える
【日時】2010年8月7日 午後16:30開場 16:45開始
【会場】広島県広島市中区袋町6番36号 広島市まちづくり市民交流プラザ 北棟5F 研修C
【会費】1000円
【内容】「Death on the silkroad」上映、イリハム・マハムティ講演
【主催】日本ウイグル協会
「Death on the Silk road」について
中国の核実験が行われた東トルキスタンでは奇病、癌の発生率が中国のほかの地方に比べ高く、核実験の影響によるものと考えられる。1998 年の7、8月にイギリスのテレビ局チャンネル4で、「Death on the Sik road」というドキュメンタリーが放送された。このドキュメンタリーで現地調査したのがウイグル人医師で、現在の在英ウイグル協会のアニワル・トフティ氏である。
アニワル氏は外科医としてウルムチの病院に勤務していたときに中国本土に住む漢人と比べてウイグル人の癌発生率が高いことに気付き2年間の調査でこれが核実験と関連があることを確信した。
1998年にアニワル氏はチャンネル4の取材班として極秘に東トルキスタンの村々を訪問し、被曝によると思われる人々の健康調査を行った。核実験は中国本土に影響が少なくなるよう、東から西に風が吹くときを選んで行われた。このため、ロプノールから西に向けて核生成物質が大量に降下したと考えられる。実際に、口唇口蓋裂ばかり、あるいは大脳未発達の赤ちゃんばかりが生まれる村もあったという。
ウイグル人の癌の発生率は70年代から急増、1990年代以降には中国全国の発病率に比べ30%以上高い数値を示している。中国政府は核実験の被害を公表せず、現地調査も許可しないため、40年以上に渡って被曝者たちは放置されてきている。